目次
新型コロナウイルス感染症の世界的流行の始まりから5年。街は活気を取り戻し、マスク姿の人もまばらになりました。「新型コロナウイルス感染症の恐怖は去った」。多くの方がそう感じていることでしょう。
でも実は、今も新たな感染者は日々発生しています。若い世代に比べると体力も免疫力も落ちやすい高齢者は、感染によって入院や予期しない医療費の負担に直面するリスクがあります。いのちと暮らしを守るために、今こそ「新型コロナウイルス感染症治療の現在地」を正しく知りましょう。
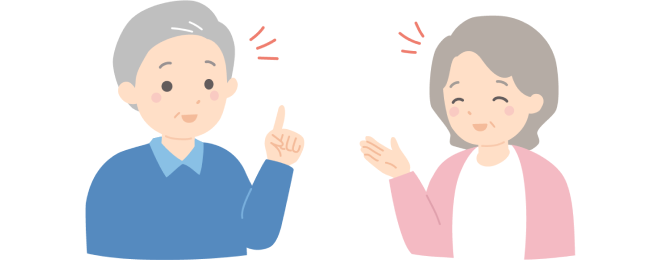
感染症法の位置付けは
「2類」から「5類」へ
2023年5月、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の分類が「2類感染症」から「5類感染症」に変更され1)、社会的な扱いも同じく5類であるインフルエンザと同様になりました。これにより、外出自粛の要請や入院の強制はなくなり、自主的な対応が基本となっています。具体的にどう変わったのか見てみましょう(表1)。
表1
2類から5類への変更ポイント
-
基本的な感染対策を行政から求められることはない
-
新型コロナウイルス陽性者や濃厚接触者になっても一律の外出自粛は求められない
-
幅広い医療機関で受診が可能
-
医療費は、1割から3割の自己負担が基本
5類になった今、世の中の感染対策意識は薄れつつあります。さまざまな施設に出入りするとき手指の消毒が必須ではなくなり、飲食店にあったアクリル板の仕切りは見なくなりました。とはいえ決して、新型コロナウイルスの新規感染者がゼロになったわけではありません。
新型コロナウイルス感染症の治療は
重症度に応じて
決まる
では、今、新型コロナウイルス感染症にかかってしまったら?
新型コロナウイルス感染症の治療は、今どうなっているのでしょうか。
ワクチンの普及や、ウイルスが重症化しにくいオミクロン株に置き換わったことで、多くの人が軽症で済むようになった一方、高齢者は、新型コロナウイルス感染症自体は軽症でも、合併症で入院が必要になる可能性があります。何よりも、症状に応じた適切な治療を受けることが大切です2)。厚生労働省では、重症度分類(表2)に応じて、治療方針を定めています。
表2
新型コロナウイルス感染症における重症度分類
(医療従事者が評価する基準)
| 重症度 | 血液中の酸素の 豊富さ |
症状や状態 |
|---|---|---|
| 軽症 | SpO₂(動脈血の酸素飽和度) が 96%以上 |
呼吸器症状なし、または咳のみ |
| 中等症 I (呼吸不全なし) |
SpO₂が93~96% | 呼吸困難、肺炎を示す症状・検査結果などがある |
| 中等症 II (呼吸不全あり) |
SpO₂が93%以下 | 酸素の吸入が必要 |
| 重症 | ー | 集中治療室(ICU)に入る、または人工呼吸器が必要 |
このような重症度別の治療方針3)を、簡単にまとめました。
軽症
特別な治療をしなくても、経過観察で自然に軽快することが多いです。ただし、特に高齢者や生活習慣病などの基礎疾患のある方は、最初は軽症と診断されても、その後に症状が進むことがあります。

中等症Ⅰ(呼吸不全なし)
入院による薬物療法が基本です。安静と十分な栄養が大切で、脱水に注意する必要があります。重症化リスク因子を持ち、特にワクチン接種を受けていない患者さんは、病状の進行に注意が必要です。
中等症Ⅱ(呼吸不全あり)
入院し、呼吸不全に対する治療を行います。
重症(集中治療)
急速に呼吸状態が悪化することがあるので、人工呼吸器やECMO(エクモ、体外式膜型人工肺)の使用が検討されます。

ここで心に留めて置いて欲しいのは、「65歳以上の感染者は、重症化するリスクが高い」4)ということ。重症化した場合、何よりも重要なのは、早期の検査・治療開始です。しかし、いうまでもなく、日頃からの「感染しない対策」「感染しても重症化しない工夫」が大切です。
新型コロナウイルス
感染症の治療の費用、
いくらかかる?
2025年3月をもって、国による医療費支援は終了しました5)。これから新型コロナウイルス感染症にかかった場合、治療はすべて健康保険の自己負担分の支払いが生じます。実際に感染した場合の治療費をイメージしてみましょう(表3)。
表3
75歳以上の新型コロナウイルス感染症の医療費の自己負担イメージ
<外来医療費>
| 2023年 5月7日 まで |
2023年 5月8日 から |
2023年 10月1日 から |
完全移行後 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来治療費、 治療薬とも全額公費支援 |
治療薬は全額 公費支援 |
治療薬は一定 の自己負担 (定額) |
外来治療費、 治療薬とも通常の自己負担 |
||
医療費の負担割合 |
1割 (住民税非課税、 年収約200万円まで) |
0円 | 1,390円 (うち薬剤費0円) |
4,090円 (うち薬剤費3,000円) |
8,000円〜10,520円 (うち薬剤費9,430円) |
| 2割 (年収約200万円〜 約370万円) |
0円 | 2,780円 (うち薬剤費0円) |
8,180円 (うち薬剤費6,000円) |
18,000円 (うち薬剤費18,860円) |
|
| 3割 (年収約370万円 以上) |
0円 | 4,170円 (うち薬剤費0円) |
12,270円 (うち薬剤費9,000円) |
31,570円 (うち薬剤費28,290円) |
|
<入院医療費>
| 75歳以上 (1割負担) |
2023年 5月7日 まで |
2023年 5月8日 から |
2023年 10月1日 から |
完全移行後 |
|---|---|---|---|---|
| 住民税非課税 (所得が一定以下) |
0円 | 0円 | 5,000円 | 15,000円※ |
| 住民税非課税 | 0円 | 4,600円 | 14,600円 | 24,600円※ |
| 年収約370万円まで | 0円 | 37,600円 | 39,800円〜 47,600円 |
39,800円〜 57,600円※ |
-
※高額療養費を適用
-
※「年収約370万」の所得区分には2割負担も含まれる。
もし重症化したりすると、医療費もかなりかかります。もちろん、高額療養制度などの助成制度で毎月の自己負担額の上限が定められているので、これらを活用すれば全額支払うことにはなりませんが、予防するに越したことはありません。
健康習慣+ワクチン接種で
発症と重症化を防ごう!
繰り返しになりますが、新型コロナウイルス感染症の危険はなくなったわけではありません。基本的な感染症対策を継続していくことで、制限のない暮らしが支えられます。今の「新しい健康習慣」7)をまとめましたので、参考にしてください。
「新しい健康習慣」として
気を付けるべき
チェックポイント
体調不良や症状がある場合は、
無理せず自宅療養あるいは受診を

その場に応じたマスクの着用や
咳エチケットの実施
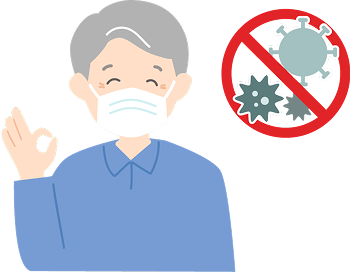
換気、密集・密接・密閉(三密)の
回避は引き続き有効
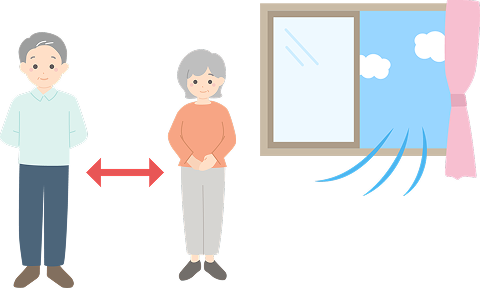
手洗いを日常の生活習慣に
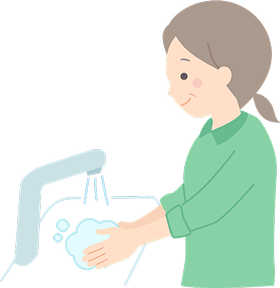
適度な運動、食事などの生活習慣で
健やかな暮らしを
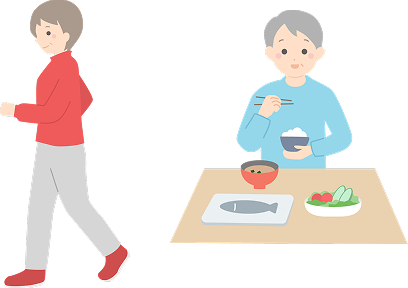
こうした健康習慣に加え、ワクチンの定期接種を考えてみましょう。ワクチン接種は、発症を抑え、重症化・入院・医療費負担などを防ぐ対策です。ワクチン接種を予防の柱とし、健康習慣と合わせて新型コロナウイルス感染症から身を守りましょう。
-
1)
-
2)
-
3)
-
4)
-
5)
-
6)
-
7)
2025年7月14日閲覧
同じタグの記事










